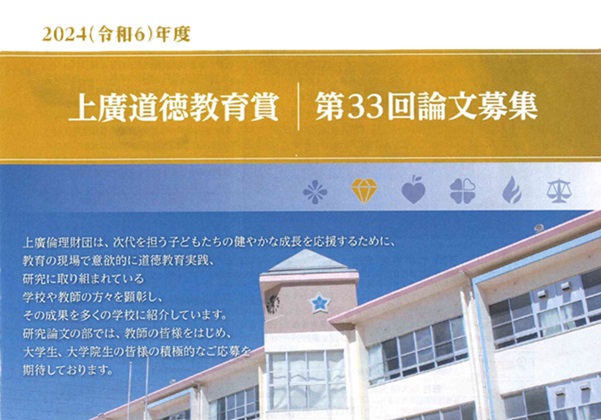お知らせ Information
募集中の助成・行事
財団事業 Activity Overview
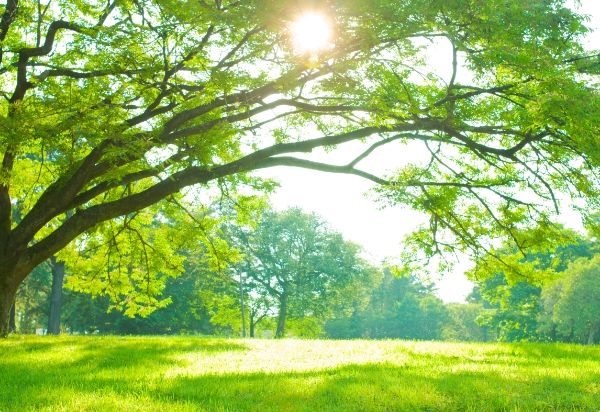
学術振興
学術振興助成では「広義の倫理」「より善く生きるための知恵や実践」「中立的視点」これら3つのキーワードを念頭に置き、社会との連携や交流、還元を行っている研究者等に支援することを目的に実施しております。
詳細を見る

学校教育
子どもたちの様々な体験を通して得た感動や、四季のなかで育まれた心を、「言葉」で表す機会を提供しています。
詳細を見る

社会文化
人の生き方や教育に関する講演会や文化活動を主催・促進することを通して、社会文化の振興を図るとともに、青少年の健全な成長を支える諸団体の活動を支援しています。
詳細を見る

研究助成
共生社会を目指して、倫理研究のより善い発展に資する取組みを支援するために、様々な研究助成を実施しております。
とくに若手研究者の育成に対しての支援を広げていきます。
詳細を見る

国際交流
世界の先端をゆく研究者や、教育現場でリーダーとなる教員が、国際的な視点で、活発に交流していくことを支援しております。
詳細を見る
財団概要 About us

上廣倫理財団は、1987年(昭和62年)文部省社会教育局(当時)の許可を受けて設立されました。その使命は倫理の研究や教育を振興することで日本のみならず世界の平和と人々の幸福に寄与する、ということです。
この使命を実現するために、私どもは、倫理を狭義の倫理学に限定せずに「人々がよりよい人生を送るために役立つ叡智やその実践」と広義に定義することにいたしました。そして、いかなる思想・価値観からも中立であることを基本方針に据えて取り組んでいます。併せて、日本人のために倫理や倫理教育という視点に縛られずに人類普遍の倫理や教育の実現を目指しています。

- 〒102-0075 東京都千代田区三番町6-3
-
- TEL 03-3261-8711/
- FAX 03-3261-8747